脳卒中センター長挨拶
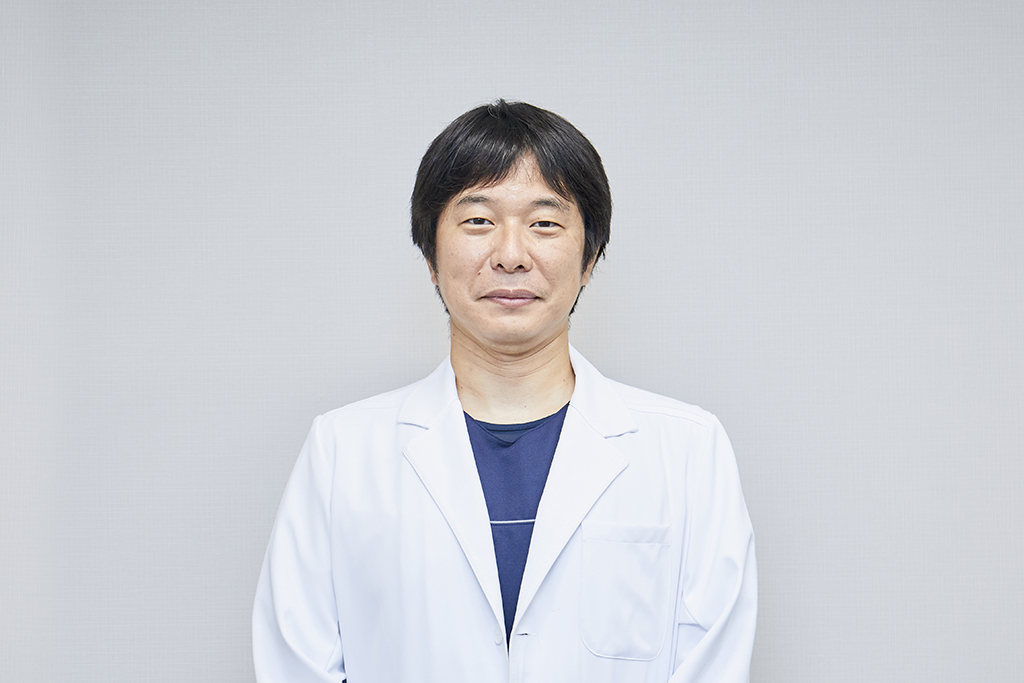
阪和記念病院は、昭和53年9月に設立されました。当初から、当時著しく不足していた脳疾患の急性期治療を重点的に行い、以来、地域の脳疾患、特に頭部外傷や脳卒中の治療に積極的に関わって参りました。
以来、脳卒中診療の進歩、変化が絶えずあり、必要な超急性期の治療体制の構築や、急性期治療と並行して行われる急性期リハビリテーション、その後の療養まで含めた診療を行うべく平成26年に脳卒中センターを立ち上げました。
現在は脳卒中学会認定の一次脳卒中センター(PSC)として地域の急性期脳卒中医療に貢献しながら、令和4年の病院移転に伴い回復期リハビリテーション病棟や療養病棟も併設し、超急性期から慢性期までの患者様の対応ができるようになりました。
脳卒中センター長 矢野 喜寛
脳卒中とは

脳卒中とは、脳血管の急性の障害により起こる病気の総称で、その字が表すように昔から「卒然として邪風に中る(あたる)」と言われ、突然発症し手足の麻痺や言語障害が出現、そしていったん発症すると有効な治療法はなく、たいていはそのまま人生を終えるものとされてきました。
脳卒中にはよく知られた病気として、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞があります。
いずれも突然発症し生命に関わる病気として緊急性が極めて高いため、以前より脳出血、くも膜下出血には手術治療を含めた速やかな急性期加療を行えるよう診療体制を整えて参りました。
しかし、脳梗塞には根本的な治療がなく、主として点滴治療とリハビリテーションが行われてきましたが、平成17年に脳梗塞に対して、tPA(組織プラスミノゲン活性化因子)が、平成22年に経皮的血栓回収術が認可され根本的に脳梗塞を治癒することができるようになりました。これらの治療は以前から行われていた手術治療などよりもさらに速やかに治療を行う必要があり、時間との闘いになるためそのための体制作りが重要になってきます。
当院ではいずれの治療も24時間365日行えるように、また以前からの歴史、経験を生かしてより速やかな治療を行えるように体制を整えております。
急性期治療後
脳卒中では、急性期の早期からリハビリテーションを行うことが重要とされ、当院でも行っております。もちろん症状が消失し、社会復帰できることが一番ですが、急性期治療が終了後も麻痺や失語などの症状が残った場合にはさらなるリハビリテーションが必要になります。
そういった場合に重点的にリハビリテーションを行うための社会制度として、回復期リハビリテーションがあります。急性期治療が終了後、必要な場合に専門施設として回復期リハビリテーションを行う病棟や病院に移っていただき重点的にリハビリを行って、社会復帰・家庭内復帰を目指していただきます。
しかし不幸にして症状が重篤で後遺症のため、リハビリテーションを行っても社会復帰が困難となって、慢性期に他の介護施設や病院での療養が必要になる患者様もおられます。
このように、脳卒中の診療には病院間の連携が重要になるため、平成20年6月に大阪脳卒中医療連携ネットワークが設立され、当院も設立当初より参加しております。また維持期の病院やかかりつけ医としての開業医の先生方にもこのネットワークの構成員となっていただき、患者様の生活の援助や再発予防などにも力を注いでいます。
さらに当院では回復期リハビリテーション病棟、療養病棟もあるため、急性期から慢性期までの治療を当院のみで行う選択も可能となっています。
スタッフ紹介
-
センター長矢野 喜寛平成15年卒
-
副部長
西 麻哉
平成22年卒
-
医長
寺田 栄作平成25年卒 -
医員
平井 信登令和3年卒

